1950年代にギブソンが生み出したTune-o-matic Bridgeは、エレクトリックギターの音作りに革新をもたらした重要な要素です。その登場以来、数々のモデルに採用され、弦高やイントネーションの調整が容易な点、そして安定したチューニングと豊かなサステインを実現する点で多くのギタリストに支持されてきました。
本記事では、Tune-o-matic Bridgeの歴史的背景や構造上の特徴、従来モデルと進化を遂げたナッシュビルタイプとの違い、さらには現代のギターテクノロジーにおけるその位置づけについて、詳しく解説していきます。ギターの音作りに興味がある方や、より深い知識を求める方にとって、Tune-o-matic Bridgeの魅力を再発見できる内容となっています。
はじめに
Tune-o-matic Bridgeは、ギブソン社の伝統と革新が融合した設計の結晶です。1950年代にテッド・マッカーティの手によって生み出されたこのブリッジは、その後多くのエレクトリックギターに採用され、今日まで音楽界に多大な影響を与え続けています。ここでは、Tune-o-matic Bridgeの基礎知識から最新の進化までを網羅的に解説します。
歴史と背景
1953年、ギブソン・スーパー400で初登場し、その革新的な設計は瞬く間に注目を集めました。翌年にはレスポール・カスタムにも採用され、ギブソンの定番仕様として確固たる地位を築きました。長い歴史の中で、その安定した構造と調整の容易さが、多くのギタリストにとって信頼の証となっています。
非常に歴史のあるブリッジですね…
調整も隙間からマイナスドライバーでササッとできるので自分でハードル低く調整できるのが魅力です。
設計と特徴
このブリッジは、弦の張力を直接支えるシンプルな構造により、弦の振動を効果的にボディへ伝達します。サドルの調整が容易で、弦高やイントネーションの細かな調整が可能なため、音の明瞭さと豊かなサステインが実現されます。また、ブリッジ本体の素材や仕上げにもこだわりが見られ、演奏性と耐久性の両立が図られています。
ちなみに筆者はTune-o-matic Bridgeのままトレモロアームを使いたいという気持ちから、下のような商品(筆者が購入したのと同じ商品が見つかりませんでした)を購入してトレモロアームを使用しています。ストラトなどに元から備えついているものに比べると気持ちチューニングが狂いやすいですが、中音域の豊かな音にトレモロアームをかけれるという利点からそのまま頻用しています!
少し高いですが興味のある人は試してみてください!
ABR-1とナッシュビルタイプの違い
初期モデルであるABR-1のコンパクトなデザインと、ワイヤーサドルによる固定方式が特徴です。対して、1970年代に導入されたナッシュビルタイプは、より大きなデザインと広い調整範囲を誇り、細かなイントネーションの調整が可能となっています。各モデルの違いは、ギターの用途や演奏スタイルに応じた最適な選択を促します。
現代の進化とその影響
現代のギターメーカーは、Tune-o-matic Bridgeの伝統を受け継ぎつつ、さらなる技術革新を取り入れています。例えば、エピフォンの「LockTone Stopbar Tune-o-matic System」は、ブリッジとテールピースのはめ込み式構造により、弦交換時の安定性とサステインの向上を実現。これにより、古典的なデザインの良さと現代のニーズを両立させた新たな進化が見られます。
従来の弦交換の時に弦の張力がなくなるとポロッと落ちてしまい、ブリッジ自体がそこそこ重い部品なのでギターや床をうっかり傷つけてしまう恐れがありましたが、「LockTone Stopbar Tune-o-matic System」はそういった心配から解放されます!より機能的な方向に進化していますね!
まとめ
Tune-o-matic Bridgeは、その歴史と共に多くのギタリストに愛され、音楽界に革新をもたらしてきました。安定したチューニング、柔軟な調整機能、そして進化を続ける設計は、ギターサウンドの幅を広げる大きな要因です。ギター選びやメンテナンスにおいて、Tune-o-matic Bridgeの特性を理解することは、理想のサウンドを追求する上で非常に有益と言えるでしょう.

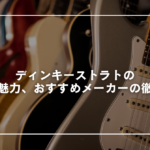
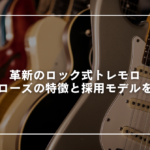
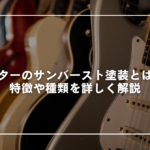
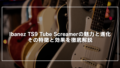

コメント